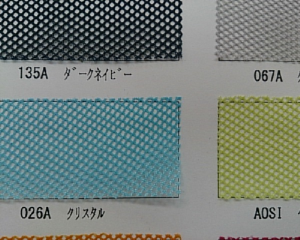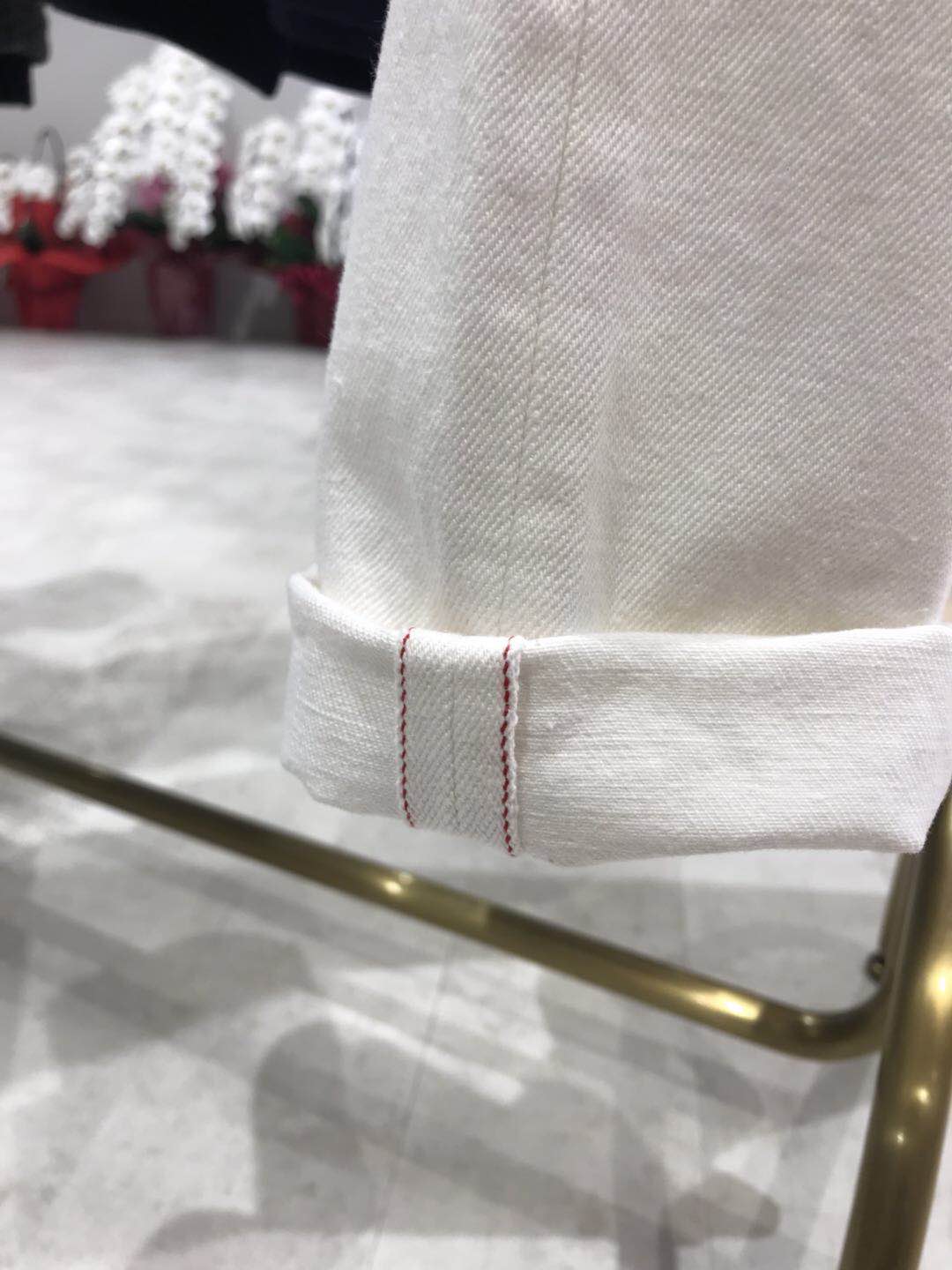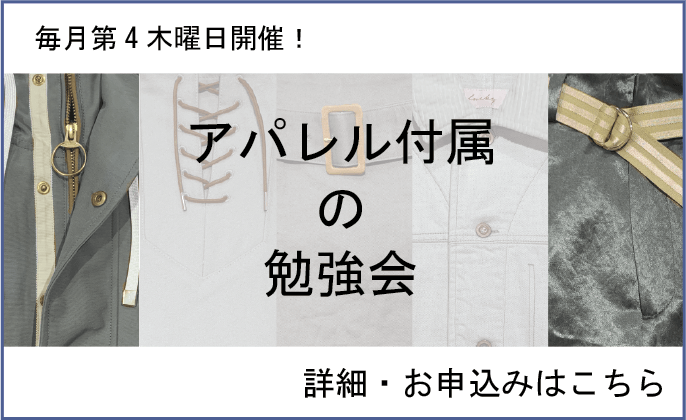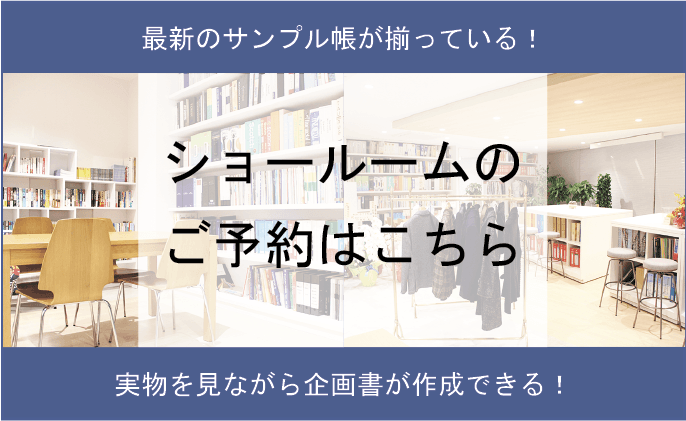簡単な繊維の話はじめました~その6
講座正藍染と本藍染めとインディゴ染
日本の藍染め
世界の各地で古来より植物に含まれた青を発色する物質として用いられてきたインディゴを用いた染色法は、国内では江戸時代に入り綿の需要の増加ともに広く行われるようになった。シルクと比べて天然染料での染色性が低い綿を染めるために藍染めの需要が共に高まり、この時期に日本の伝統的な藍染め技術も確立されたと考えられる。
日本伝統の正藍染
日本の藍染は元来、蓼(たで)という植物を発酵させた“すくも”と呼ばれる染材に灰と
灰汁を加えて甕(かめ)で7日から10日くらいかけて自然発酵させた染液に糸や生地を浸して乾かす作業を繰り返して染め上げる大変手間と時間を要する染色です。日本の藍の生産量は明治時代の前半に最盛期を迎え全国におよそ5万町歩の藍畑があったそうです。生産量は徳島県が最も多く次いで三重、岡山、広島、埼玉、栃木の順で多く生産されていましたが明治の後半になるとインド藍の輸入が増え、その後人造藍(インディゴ染料)が入ってくると国内産の藍は安価で大量に生産ができるこれらの藍や人造藍に取って代わられ藍畑も一気に激減する。しかしこの化学的な藍染めの品質の悪さに気づいた消費者は藍から離れ染色は輸入化学染料の時代へと切り替わっていく。国内の藍栽培はその後、多少の増減しながら現在は20町歩程の藍畑で生産されている。
本藍染めとは
本来の伝統的な国産の“すくも”を灰汁だけで建てる(本建て)正藍染めは技術的に熟練を要しコストも高いために現在ではインド藍などを混ぜて石灰や苛性ソーダ、ハイドロ等の還元剤を使って染めている染屋や染色工場が多く、それぞれの染屋や染色工場が原料や技術的な工夫をし伝統的な正藍染めとは区別してこれらの藍染めを本藍染めと呼んでいる場合が多いです。元来は本藍染めという言葉も化学物質やふすま、糖類などを一切使わない本建てを行う伝統的な染色方法を指している言葉であったのが現在では天然の藍のすくもを使用した染という意味に変わって来ているようです。
人造藍(インディゴ染色)
合成インディゴはドイツの化学会社がその組成を分析して大量に合成することに成功して作られました。従って天然藍もインディゴ染料もブルーを発色する物質は同じで、日頃身に着けるジーンズのほとんどが合成インディゴで染められているのは皆様も御承知の通りです。水に溶けない暗青色物質のインディゴを染色する際に還元(アルカリ性)させて溶解し繊維に浸透させてから空気に触れさせて酸化することによりインディゴ独特のブルーが発色するので現在のインディゴ染めは強力な還元剤のハイドロサルファイトと苛性ソーダを使用してインディゴを還元して染色しています。
藍染めの魅力
古来より世界各地で植物に含まれるインディゴを利用した青の染色が行われてきました、日本の中でもアイヌではエゾタイセイ、本州地域では蓼藍、八重山ではリュウキュウアイと利用されてきた植物は地域によって違っています。2020年の東京オリンピックのエンブレムのデザインにも藍色の市松模様が使われていますよね。でも昨今の藍染めブーム、ジャパンブルーなどと言っても日本国内産の藍を伝統的な技法で染めているのはほんのごく一部で国産の藍の生産量が増えているわけでは無いのです。古来より世界中で利用され愛されてきたインディゴブルー。伝統的な藍染め技法を守りながらも新しい藍染めを創造していくクリエーションの中心に日本がなっていくと楽しいですね。
弊社でも各種藍染の生地も取り扱っております、お問い合わせはコチラまで
では~
TAKIZAWA
生地のことなら何でもお聞きください。趣味がトレッキングや山登りなので、アウトドアウェアにもちょっとだけ詳しいです。「テキスタイルコラム-Textileから見た世界」を担当しています。私のミッションは失われつつある美しい地球環境を500年後の子孫に残すこと…誇大妄想Innovatorです(笑)
最新記事 by TAKIZAWA (全て見る)
- テキスタイルコラム-エピソード②スモックコート - 2022年6月24日
- テキスタイルコラム-エピソード①羊飼いの偉人たち - 2022年6月17日
- テキスタイルコラム-羊毛を効率的に収穫する方法 - 2022年6月10日
関連記事
- PREV
- ちょっと気に成る良い付属シリーズ
- NEXT
- ジャケットにいつもと違うボタンを選んでみる!?